暇なときに 日本にとってインフレは脅威なのか? ~90年代の世界経済から考える~
- 篠原竜一

- 2022年4月7日
- 読了時間: 9分
私は1988年に社会人生活をスタートしたが、1990年代は、どんな時代だったのだろうか?当時は、これからは日本の時代だと全く逆のことを考えていたが、今から振り返ると、アメリカが繁栄、日本が衰退した時代となってしまった。
最初に日本にとってどんな時代だったのか振り返る。
官僚と銀行員が作り出した護送船団方式によって、勤勉な国民の預金が資金不足のセクターへ貸出を通じて流れる仕組みを構築した日本は、信じられないスピードで経済発展した結果、80年代の日本はアメリカとの経済格差をどんどん縮めていた。89年12月末の日経平均株価は、38,915.87の史上最高値を示現した。
当時は気がつかなかったが、おそらく80年代の日本経済は先進国として成熟期に入っていたのだと思う。経済学部で学び、銀行で働いていたにもかかわらず、日本経済が強い需要に支えられる形で成長していたことに何の問題意識を持たなかったことが悔しくて仕方ないが、当時の経済学者、官僚、銀行員たちが中心になって議論すべきだったことは、供給サイドに注目し、潜在成長力をどうやって引き上げていくかということだったのだろう。
80年代から90年代の日本経済を牽引したのは大企業だったが、銀行は不動産融資に傾斜するのではなく、官僚を巻き込みながら、新しい価値を生みだすためにスタートアップをサポートし、その過程で新しい産業分野を生みだし、産業構造の高度化を実現するエコシステムを構築すべきだったのだと思う。そうした取組みが新たな需要を生みだし、経済成長を持続できるようにすべきだったが、バブルの崩壊により90年代、銀行はそれどころではなくなり、日本企業はリストラせざるを得ない状況に追い込まれていったのだろう。バブル崩壊以降の日本は、本格的なインフレで苦しんだことはない。賃金上昇を伴う経済成長を実現できなかったということと同義だと私は考えている。
一方、90年代前半のアメリカは日本以上にもがき苦しんでいたことに注目すべきだろう。89年12月末のダウ平均株価は、2,753ドルだ。アメリカが巨額の貿易赤字・財政赤字のいわゆる“双子の赤字”、さらには労働生産性の低下に苦しんでいた時代だ。何故90年代半ば以降のアメリカは繁栄できたのか?
90年代を前半と後半に分けてアメリカ経済を考えてみる。
80年代後半はアメリカの中央銀行であるFRBがインフレ抑制のため金融引締政策を実施していた。90年代に入り、金利上昇の悪影響に加え、湾岸戦争で石油価格が高騰した影響で消費者の実質ベースでの所得が減少、失業率が上昇し、先行きの不透明感が強まり、個人消費が落ち込んだ。企業も消費の減退に対応して生産調整や在庫圧縮、人員削減を伴う大規模なリストラを実施した。こういった経済状況の中、92年の大統領選挙では、現職のジョージ・ブッシュ共和党候補は民主党のビル・クリントン候補に敗れ、再選を果たせなかったと言われている。しかしながら、景気を減速させてでもインフレ率の上昇を抑え込む政策をブッシュ政権が行ったことが、その後のアメリカの繁栄に繋がったことに疑いの余地はない。
この90年代前半(91-95年)の実質経済成長率の平均は約2.4%。クリントン政権が財政赤字削減、企業がリストラに取組んだことにより、力強い経済成長は実現できず、アラン・グリーンスパンFRB議長は、金融緩和政策を実施し、景気の押上げに取り組んでいた。当時のアメリカでは、アメリカ国民には実感がわかないジョブレスリカバリーという言葉が良く使われ、アメリカ人が大学院で日本的経営を学んでいた。
しかしながら、90年代後半(96-2000年)の実質経済成長率の平均は約3.3%で、クリントン大統領、ロバート・ルービン財務長官、グリーンスパンFRB議長に対する市場の信頼感は絶大だった。強いドル政策が資本をアメリカへ動かし、95年にダウ平均株価は、4,000ドル、99年には10,000ドル乗せを示現、この10年で株価は実に3倍以上の値上がりを実現したのだ。アメリカの財政は黒字となり、企業は設備投資、雇用拡大を積極的に行い、家計も消費を活発化し、力強い経済成長を実現した。
アメリカには、非常に厳しい状況でも、リスクをとる投資家と起業家が常に存在していたことが日本とは大きく状況が異なった。マイクロソフトとアップルが70年代半ばに設立され、しのぎを削り、90年代半ばにはパソコン、インターネットが急速に普及、93年に設立されたアマゾンがオンラインショップの先駆けとなった。その後98年にグーグルが設立され、新しい価値を生みだし、生産性を大きく向上させ、経済成長を実現したのである。スタートアップの中から急速に成長する企業が現れるようになり、90年代半ばには、アメリカではスタートアップへの投資額が急速に増えた。この動きは今でも変わらない。現在のダウ平均株価は34,000ドル台と株価は2000年に入ってから更に3倍以上の値上がりを実現している。
どうして日本ではアメリカのような動きが起こらなかったのか?
80年代の民間研究開発費の対GDP比は日本がアメリカを上回っていた。当時の日本では、革新的技術・新規事業に融資し育成する役割を担っていたのは銀行だったが、バブル崩壊を受け、銀行がバランスシート削減に取り組んだことがこの時代の成長を抑え込んでしまった大きな要因だと思う。
90年代のアメリカの景気拡大の大きな特徴は何だろう?
物価の低位安定と低い失業率が両立していたことだ。インフレ率の加速が景気拡大の足枷となり、金融引締政策などを通じて、やがて拡大が終わるというパターンはもはや過去のものと市場参加者が考えるようになった。
現在の世界経済は、新型コロナの感染拡大を受け、グローバルサプライチェーンが目詰まりしたことを主因に、インフレ率が上昇する中、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で原油・商品価格が急騰し、更なるインフレ率の上昇が懸念されている。
誰にも答えられない問題だが、アメリカ経済はこのインフレ率の上昇に耐えられるのだろうか?
足許の経済指標を見る限り、アメリカ経済は堅調だ。3月のアメリカの雇用統計によれば、時間当たり賃金は+5.6%(前年比)と順調に伸びている。たしかに景気は減速するかもしれないが、直ちにリセッションを心配する必要はない。心配する必要が出てくるとしても、それは来年以降の話だろう。2月のアメリカの個人消費支出(PCE)物価指数は、前年同月比6.4%上昇、コア指数も5.4%上昇、83年以来の高水準となっているのはとても気になる。インフレ率を抑え込むために、金融引締が実施され、80年代後半のような経済状況になってしまうリスクはたしかにある。住宅ローン金利(30年固定金利)も4%台後半まで上昇している。株式市場・不動産市場・債券市場が混乱し、実体経済に悪影響を与えるリスクは頭に入れおく必要があるだろう。
斯かる状況下、FRBは、インフレ率の上昇を抑えることを目的として、金融政策を金融引締政策へ大きく転換した。今後FF金利の誘導目標の引き上げのみならず、FRBのバランスシートの削減を実施する方針で、米国債、エージェンシー債、モーゲージ債を売却することになる。アメリカの金利上昇は始まったばかりだ。FRBによる利上げ並びにバランスシートの削減が今後の景気・物価にどのような影響を与えるかが今後のポイントだ。
シリコンバレーへの資金が細るようだと心配だが、スタートアップエコシステムが機能し、生産性を押し上げることが可能であれば、アメリカの賃金水準はこれからも伸びていく。当面の間、労働生産性の動向に注目すべきだろう。
日本はどうか?
日本のスタートアップによる資金調達額はシリコンバレーを大きく下回っているが、2021年にはその調達額はアフリカのスタートアップによる資金調達をも下回ってしまった。世界の投資家の眼には、日本よりもアフリカの方がより魅力があると映っているのだろう。生産性を大きく押し上げるような新しい価値を生みだすことが重要課題であるにもかかわらず、日本ではその土壌が広がらない。斯かる状況下、日本のインフレ率が上昇していけば、非常に厳しい経済状況になる可能性が高いとしか言いようがない。
少なくとも日銀が心配していることはインフレ率の上昇ではなく、景気だ。現状の日銀の金融政策は、FRB、ECBの政策と方向が逆だ。とても気になる。FRBだけではなく、欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのナーゲル独連邦銀行(中銀)総裁は、3月のユーロ圏の消費者物価指数(HICP)速報値が、前年同月比7.5%上昇、食品とエネルギーを除くインフレ率も3.2%に加速したことを受け、ECBは行動を起こす必要があるとの見解を示している。
そんな中、日本銀行は異次元の金融緩和政策を変更する予定はない。需給ギャップが依然マイナスである国の中央銀行としては、当然の判断なのかもしれないが、金利差は拡大するだろう。こういう時には当然ながら為替が動く。ポジション調整をこなしながら、これからも円安が続くだろう。金融引締に繋がりかねない金利の上昇は受け入れられないという日銀の考え方はわかるが、10年物日本国債が0.25%という超低金利の水準にある今、自然な形で金利が上昇することがドル円相場を安定させ、輸入物価の更なる上昇を防ぐことが出来るのだとすれば、日本にとって決して悪いことではないはずだ。財務省が円買介入を実施するという噂も流れているが、本当に実施されるとすれば、東京市場は自由な市場ではなくなってしまう。日銀と財務省が力で金利水準と為替の水準を決めてしまう。市場の信頼性は失われるだろう。
3末にかけて実施した連続指値オペは、日銀は、0.25%を上回る金利上昇は受け入れないという意味であり、日銀は否定するだろうが、世界中に”円を売ってください”と宣言しているような政策だ。日本のインフレ率はこれから更に上昇するだろう。賃金上昇を伴う景気回復を実現できない限り、日本のじり貧状態は続く。明らかに更なるインフレ率の上昇リスクが高まっている状況下、自国通貨安政策に繋がる可能性のある政策を日銀が積極的に実施しているのだ。
インフレ率の上昇は日本にとって脅威としか言いようがない。経済状況は大きく異なるものの、このままでは、90年代のような日本経済の状況に陥ってしまう可能性が高まっている。
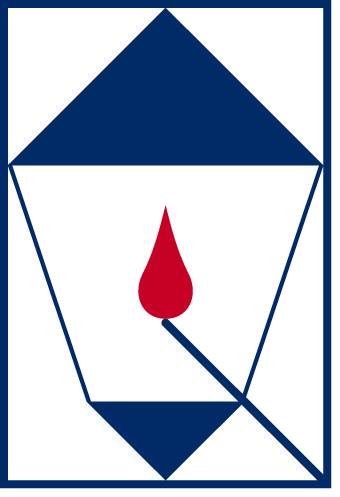



コメント