篠原金融塾 年末特別号 グローバルマーケットウィークリー 12/24/2021
- 篠原竜一

- 2021年12月25日
- 読了時間: 9分
バイデン米大統領のリーダーシップの下で2021年のアメリカの実質経済成長率は5%を超えそうだ。就任後1年間で約600万人の雇用が創出され、失業率は4.2%まで低下した。それでも支持率は低迷している。問題は山積みだ。サプライチェーンが混乱したことを主因にインフレ率が上昇し、コアPCEは4%台の半ばとFRBがターゲットとする2%を大きく上回っている。加えて、足許ではオミクロン株の感染拡大がアメリカ全土に広がっている。
アメリカの中央銀行であるFRBによるアメリカ経済の現状認識は以下の通りだ。
ワクチン接種の進展や強力な政策支援を背景に、経済活動と雇用に関する指標は引き続き力強さを増している。パンデミックに最も大きな打撃を受けたセクターは、ここ数カ月で改善したが、新型コロナウイルスの影響を受け続けている。ここ数カ月、雇用の増加は堅調で、失業率は大幅に低下している。パンデミックや経済活動の再開に関連した需給の不均衡は引き続き、高水準のインフレ率をもたらしている。経済および米国の家計・企業への信用の流れを支援する政策措置などを反映し、全体的な金融情勢は依然として緩和的だ。経済の道筋は引き続きウイルスを巡る状況に左右されるだろう。ワクチン接種と供給制約の緩和が進めば、経済活動および雇用の拡大持続とインフレ抑制を後押しすると予想される。ウイルスの新たな変異株による影響を含め、景気見通しに対するリスクは残っている。
ポイントは、高水準のインフレ率についての認識を一時的なものという見方からアメリカ経済にとってリスクという見方へ変えたことだ。テーパリング(量的緩和の解除)が進み、2022年春には、いよいよアメリカの金融政策は引き締められることになる。
そんな中2022年がどんな年になるのかを今考えている。
30年前の12月、私は92年1月からロンドンで市場部門のトレーニーとして派遣されることが決まっており、その準備に取り組んでいた。92年と言えば、ポンド危機の年だ。その年の9月に英ポンドへの売り浴びせは激しさを増し、9月15日には変動制限ライン(上下2.25%)を超えた。9月16日にはイングランド銀行がポンド買いの市場介入に加えて、公定歩合を10%から12%へ引き上げ、さらにその日のうちにもう一度引き上げ15%としたが、それでも売り浴びせはとまらず、英国がERM(欧州為替相場システム)から脱退することになった年だ。
今から思えば、各国間の金融政策の方向性の違いが引き起こす問題、外国為替市場、マネーマーケット、流動性管理、金融政策、財政政策など、多くのことを学んだ年だったが、トレーニーにとっては、あまりにも市場の値動きが激しすぎて辛い一年だった。
あれから約30年。来年は92年同様、何か激しいことが起こるような気がしている。
2022年のマーケットは久しぶりにFRBによる利上げに対応することになる。日銀による金融政策には大きな変化は考えにくい。FRBは助けてくれない。米国債・モーゲージ債の購入は行わないし、利上げを実施する。かなり激しい相場を覚悟しておいた方が良い。金利上昇相場を甘く考えるととんでもないことになる。また、地政学的にも政治が安定していない時には何かが起こる。日本の立場で考えると台湾情勢からは目が離せない。
もう少し長いスパンで考えてみる。
先進各国の賃金水準が上昇する中、賃金上昇を実現できなかったどころか実質賃金が低下してしまった日本。日本は世界的に見て、良く言えば物価の安い国、悪く言えば貧しい国になってしまった。そんな中、日本の少子高齢化は待ったなしで進展している。国立社会保障・人口問題研究所は、約100年後の日本の人口は、約5,000万人にまで減少するという予測をしている。景気見通しとは異なり、出生率と死亡率、並びに移民政策が大きく変わらない限り、人口予測は大きくは外れない。だとすれば経済規模は小さくなる可能性が高い。
こういう話をすると、「日本は賃金も安いが物価も安いので、実質的な生活水準は先進各国とあまり変わらない」「日本は貧しくない、引き続き世界第3位のGDPを誇る先進国であり、悲観的過ぎる」と反論されることが多い。しかしながら、新しい価値が生み出され、経済が成長し、物価も上がるが、賃金も上がる国の方が良いことは明らかだ。「君は悲観的過ぎる」と私を批判していても、何の解決にもならない。今後は日本以外で職業を見つけることを考えた方が良いかもしれないと若者にアドバイスしたくなるほど、日本はどんどん貧しい国になっているという事実を受け入れるべきだと私は思う。
戦後の日本は世界一優秀な官僚と銀行員が護送船団方式を通じて金融システムの安定化を実現、勤勉な日本国民が安心して銀行に預金を預ける仕組みを構築した。銀行はこの預金を資金不足の分野への貸出を通じ日本経済の成長を支えた。そして、企業は新しい価値を生み出すべく研究開発に取り組み、その後の高度経済成長を実現し、敗戦後たった19年後には東京オリンピックを開催出来るほど日本は復興した。しかしながら、皮肉にもこの間接金融の仕組みにより大量に銀行に流入した資金が不動産バブルを起こすきっかけとなり、その崩壊により、全ての歯車が狂いだしてしまった。
バブル崩壊後の対応を今更議論しても仕方がないが、不良債権処理にあまりにも長い時間をかけてしまったこと、物凄く真面目に反省してしまったことにより、リスクをとって前向きなビジネスを展開することよりも、リスク回避を優先するような雰囲気が国全体に醸成されてしまったことがとても残念だ。
失われた30年。決して日本人が怠惰になったわけではない。各人が自分の持ち場で必死に働いてきたにもかかわらず、イノベーションを起こすことが出来ず、新しい価値を生み出すことが出来なかった30年と言い換えることも出来る。
グローバリゼーションとは効率化と多様化の歴史であり、経済面に注目すると物価を下げる効果がある。貿易障壁が取り払われると、日本企業はより安価な輸入品と競争せざるを得なくなり、技術の発達や貿易自由化に促され、企業は人件費の安い国々に生産を委託するようにもなった。グローバリゼーションが進展する中、企業努力により世界中に物流網を構築、効率化を進めてきたが、新型コロナの悪影響はそのサプライチェーンを直撃している。今後、原材料、部品の調達コストの上昇は避けられない。賃金水準が上がらなければ、日本人の生活は苦しくなる。仮に企業努力により価格への転嫁を避けることが出来たとしても、日本はますます物価の安い国に、貧しい国になってしまう。
我々日本人が今考えないといけないことは、新しい価値を日本で生み出せない状況が今後も続いてしまうのであれば、諸外国の富をうまく日本に取り込む工夫が必要になるということだろう。菅前首相が取り組んでいたインバンド政策は日本にとってとても重要な政策の一つだ。そしてイノベーションを通じて今後の成長が期待できる海外への投資は不可欠だ。
2016年のブレグジット、トランプ前米大統領の関税発動など反グローバリゼーションの動きに加え、新型コロナウイルスの世界的な流行により、世界各国が国境を再び意識するようになり、世界各国が水際対策を強化、入国禁止などを実施したことで、結果として保護主義的な政策(反グローバリゼーション)を実施しているような状況になっている。この動きは経済的には非効率的で、物価を上げる方向に働くことは明らかであり、2022年は今年以上に世界中のインフレ率の動向が気になる年になりそうだ。
このまま国境を強く意識するような反グローバリゼーションの動きは続くのか?
年初は、足許のオミクロン株の感染拡大を受け、残念ながら国境を強く意識することになりそうだ。しかしながら、新型コロナウイルスに対するワクチンに加え、治療薬の開発を通じて、状況は改善していく。世界中の人がスマホを手にし、情報を収集、発信することが可能になった今、政治的にグローバリゼーションの流れを止めることは出来ないと私は思う。
モバイル、クラウド、ソーシャルにより情報を収集、蓄積、共有していく新しいビジネスモデルは、今後も暗号資産、NFT(非代替性トークン)、ブロックチェーン、DAO(自立分散型組織)、メタバースなどの登場で、更に新しい価値を生み出すでしょう。この世界に国境はなく、グローバリゼーションは今後も進展する。こうした世界的な流れに対して、日本企業が積極的にチャレンジ出来るか否か、積極的にチャレンジする企業をサポートできるかどうかが大きなカギになる。
そんな中、私は今13億人の人口を抱えるアフリカに注目している。中位年齢は19歳と圧倒的に若く、今後も人口が増加することが予想されており、2050年には25億人と世界の4人に1人はアフリカ人になると言われている。まさにラストフロンティアである。アフリカの抱える多くの社会課題をリスクと考えている人にとっては投資先としては、全く魅力的ではないだろう。確かに社会課題を解決できないまま、人口増加が続けば政治的にも経済的にも安定は望めないが、多くのスタートアップがアフリカの抱える社会課題をビジネスの機会と捉え、その解決に取り組んでいる。シリコンバレー、欧州からアフリカのスタートアップには多くの資金が流入しており、確かに日本企業にとって「アフリカは遠い」が、それではこれからの陣取り合戦に参加することは難しい。
意外と知られていないが、既にユニコーン企業となっているアフリカでオペレーションを展開する企業は11社もある。日本企業を上回る数の会社が新しい価値をアフリカで生み出している。私は、この成長のポテンシャルとそこから生まれる富をうまく日本に取り込むことに2022年は注力したいと考えている。
2022年が素晴らしい一年となりますように!

株式会社ランプライターコンサルティングは、当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。当サイトでは、信頼できる情報源から得た情報を、確実に掲載するようあらゆる努力をしておりますが、株式会社ランプライターコンサルティングは、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。当サイトに掲載されている全ての情報は、その時点の情報が掲載されており、完全性、正確性、時間の経過、あるいは、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。また、あらゆる種類の保証、それが明示されているか示唆されているかにかかわらず、また業務遂行、商品性、あるいは特定の目的への適合性への保証、また、これらに限定されない保証も含め、いかなることも保証するものではありません。
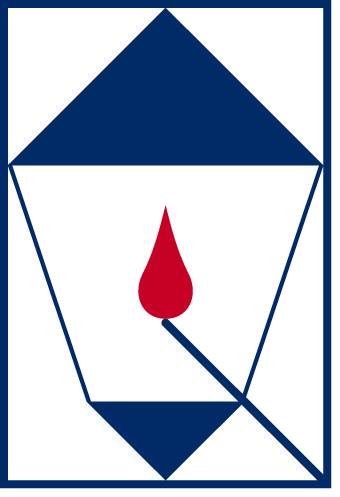



コメント