篠原金融塾 グローバルマーケットウィークリー 11/21/2025
- 篠原竜一

- 2025年11月23日
- 読了時間: 3分
引き続き円安が止まらない。
アメリカの金融政策は、2025年10月のFOMCで、2会合連続で0.25%の利下げを決定し、現状のFF金利は 3.75~4.00%。
インフレ率はピークを過ぎて年率3%程度まで低下したものの、FRB目標の2%を上回っており、ここからは慎重に金融政策を進めるという向きも増えてきた。
しかしながら、2026年にかけて段階的な金利引き下げを続け、米連邦準備制度理事会(FRB)は景気減速とインフレ鈍化を背景に、政策金利を中立水準(3%前後)へ近づける方向で調整を進めるという見方が主流だ。
FRBにとって不確実な要因としては、追加関税や移民政策が景気・物価にどのように影響するかという点だろうが、日米金利差縮小は、円安圧力を緩和し、円高方向に振れてもおかしくない。
そんな中円安が止まらない。
国債増発に依存した積極財政が継続することの危険性を意識し、債券価格下落=円売りという連動が強まっているとは思えないが、仮にそうだとすれば、金利差縮小でも円高に反応しづらくなるのかもしれない。
エネルギーや原材料の輸入増加により、貿易赤字が慢性化。今後は、輸出産業の競争力低下もあり、外貨獲得力が弱まるとすれば、市場心理はより円安方向に傾くだろう。
生活面では、輸入品価格の上昇を受け、食料品・エネルギーコストがこれからも増えていく。その結果、家計の実質所得が減少することに。自動車など輸出企業やインバウンド産業にはプラス効果があるものの、それで埋め合わせを出来るとは思えない。
そんな中、アメリカからは興味深いニュースがはいってきた。ミランFRB理事は、グローバルなシステム上重要な銀行(GSIB)に関し、国際金融システムでどれだけ重要な役割を果たしているのかを測定する資本要件とされる「強化補完的レバレッジ比率(eSLR)」の計算から米国債を除外するよう金融規制当局に求めている。
ミラン氏は米国債を要件から除外すれば、金融の混乱が起きた際に銀行が米国債の保有の意欲を失わなくなるため「保護」できると主張している。
これが実現すれば、米国債に資金が流入し、大きく金利が低下する可能性もあることは頭に入れてきたい。為替、株式市場にも大きく影響を与えることになるかもしれない。

株式会社ランプライターコンサルティングは、当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。当サイトでは、信頼できる情報源から得た情報を、確実に掲載するようあらゆる努力をしておりますが、株式会社ランプライターコンサルティングは、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。当サイトに掲載されている全ての情報は、その時点の情報が掲載されており、完全性、正確性、時間の経過、あるいは、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。また、あらゆる種類の保証、それが明示されているか示唆されているかにかかわらず、また業務遂行、商品性、あるいは特定の目的への適合性への保証、また、これらに限定されない保証も含め、いかなることも保証するものではありません。
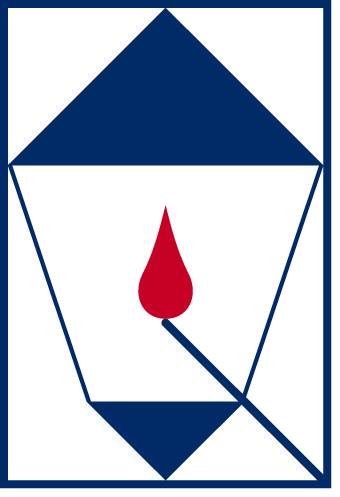



コメント