篠原金融塾 日銀による連続指値オペ グローバルマーケットウィークリー 4/1/2022
- 篠原竜一

- 2022年4月2日
- 読了時間: 9分
2月のアメリカの個人消費支出(PCE)物価指数は、前年同月比6.4%上昇、コア指数も5.4%上昇、83年以来の高水準となった。また、金曜日には3月のアメリカの雇用統計が発表されたが、非農業部門の就業者数は前月比43万1000人増と予想は下回ったものの、失業率は3.6%に低下、時間当たり賃金は前年同月比で5.6%の上昇となった。アメリカ経済は引き続き堅調だ。
そんな中、今週最も市場の注目を集めたのは、日銀による連続指値オペだ。指値オペの話の入る前に、そもそもイールドカーブ・コントロール(YCC)とは何か、導入した背景を確認しておこう。
YCCは、2016年9月の日本銀行の金融政策決定会合において、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の柱のひとつとして、これまでの金融政策の総括的検証を踏まえて導入された。短期金利のマイナス金利政策に加え、10年物国債の金利が概ねゼ0%程度で推移するように目標値を設定し、買入れを行うことで短期から長期までの金利全体の動きをコントロールすることを目的としている。そして日銀は、YCCを実施するにあたっては、指定する利回りで国債買入れを行う「指値オペ」を導入した。
YCC導入の背景についての日銀の説明は以下の通りだ。
「量的・質的金融緩和」は、主として実質金利低下の効果により経済・物価の好転をもたらし、日本経済は、物価の持続的な下落という意味でのデフレではなくなった。この実質金利低下の効果を長短金利の操作により追求する「YCC」を、新たな枠組みの中心に据えることとした。その手段としては、マイナス金利導入以降の経験により、日本銀行当座預金へのマイナス金利適用と長期国債の買入れの組み合わせが有効であることが明らかになった。これに加えて、長短金利操作を円滑に行うための新しいオペレーション手段を導入することとした。
当時のことは鮮明に覚えているが、Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Controlと英語に訳された時にはとても違和感があったことを覚えている。日銀が国債金利の上限・下限を示すYCCを新たな枠組みの中心に捉えるにもかかわらず、何故Yield Curve Control with Quantitative and Qualitative Monetary Easingと訳さないのだろうと同僚と議論したものだ。
足許日米の金利差が拡大する中、円安が進んでいる。そんな中、日銀は3月28日午後に「指値オペ」を実施、645億円分の国債を買い入れた。午前のオペでは、日銀への売却に応じる金融機関はなかったが、午後のオペでは、日銀への売却に応じる金融機関が現れた。さらに日銀は、長期金利の上昇を抑えるため、31日まで3日間、満期までの期間が10年の国債を対象に、利回り0.25%で無制限に買い入れる「連続指値オペ」と呼ばれる臨時の措置を実施した。29日には、指値オペによっておよそ5200億円分の国債を買い入れたほか、30日は指値オペとは別に予定されていた国債の買入れ措置で当初の2.5倍に増額し、およそ2兆3,000億円分を買入れた。日銀が一連のオペで国債を大量に買い入れた結果、31日の長期金利は一時、0.21%に低下した。
日銀は現状の金融政策の一環として、長期金利をゼロ%程度に、具体的には「プラスマイナス0.25%程度」の変動幅で推移するよう調節するとしている。アメリカの利上げを受け、長期金利の上昇圧力が強まるなか、日銀は長期金利の上昇を抑え込むため、指値オペをはじめ、必要な対応をとるとしている。
なぜ円安が進む中、連続指値オペを実施したのか?
日銀は、経済情勢を以下のように分析している。
わが国の景気は、感染症の影響などから一部に弱めの動きもみられるが、基調としては持ち直している。個人消費は、持ち直しが一服している。先行きは、感染症によるサービス消費への下押し圧力や供給制約の影響が和らぐもとで、資源価格上昇の影響を受けつつも回復していくとみられる。輸入原材料価格の高騰等による家計や企業のマインド変化には注意が必要だが、わが国経済は、感染症の影響が和らぐもとで、サービス消費を中心に持ち直していくとみられる。
最近の資源価格上昇により、わが国の交易利得は、2008 年頃と同様、悪化する可能性がある。ただし、今次局面は、感染症の影響による落ち込みからの回復過程にあるほか、いわゆる「強制貯蓄」が家計の実質所得減少のバッファーとして作用することも期待されるため、内需の耐性は 2008 年当時よりも高いとみられる。資源・穀物価格の高騰を受けた物価上昇に対する各国中銀の政策対応により、海外経済が下押しされる可能性がある。
ウクライナ情勢の帰趨は、不透明な部分が多く、その内外経済への影響は不確実性が高い。国内経済には下押し圧力がかかるリスクが懸念される。ロシアによるウクライナ侵攻で不確実性はきわめて大きくなった。資源・食料価格の上昇、地政学的リスクの顕在化は経済に強い下押し圧力をもたらし得る。ロシア等に対する経済制裁を受けて、現地に投資してきた本邦企業の活動が制約を受けているが、モノやお金の流れが滞ることによる影響は時間をかけて発現することから、今後、更に制限や負荷が増える可能性がある点には注意が必要である。
かつては保守的であった年金基金等も、低金利環境下で債券から株式などの高リスク資産に投資先を移してきた。ウクライナ情勢や欧米の金利上昇の影響によりリスク資産価格の大幅な調整が起こる場合には、そうした先にも大きな影響が及ぶおそれがある。
女性や高齢者による労働供給の更なる増加は難しいため、経済の回復とともに中間層の賃金が上昇しやすい環境になっていくとみられる。
また、物価については、以下のように分析している。
消費者物価の前年比は、携帯電話通信料の引き下げの影響がみられるものの、エネルギー価格などの上昇を反映して、0%台半ばとなっている。先行きの消費者物価は、原油価格の動向や政府の対応次第ではあるが、エネルギー価格の上昇を主因に、4月以降、はっきりとプラス幅を拡大し、当分の間は2%程度の伸びが続く可能性がある。先行き、マクロ的な需給ギャップの改善や中長期的な予想物価上昇率の高まりなどを背景に、基調的な物価上昇圧力は高まっていくとみられる。
消費者物価の前年比は、2022 年度前半は資源価格の高騰等によって2%近傍で推移するとみられる。ただし、2022 年度後半以降は、資源価格が反落した場合における下振れリスクにも注意が必要である。
企業がコスト転嫁する品目が拡がっているように見受けられる。これは、企業が、同業他社の動向やエネルギー価格等の上昇といった消費者に理解されやすい事情の存在により、以前よりも値上げに対する消費者の納得感を得られるだろうと考えているためとみられる。企業物価が歴史的な伸びを続ける中、消費者物価についても基調的な上昇圧力が徐々に高まってきているように窺われる。わが国に根付いているとみられる値上げに否定的な同調圧力が薄れ、値上げ許容度の改善が拡がっていくか注目している。
エネルギー関連のほか、食料品等でも値上げが確認されるものの、企業物価の上昇に比べれば、小売価格への転嫁は現時点で限定的である。これは、内需の回復が十分ではなく、企業にとって製品価格へのコスト転嫁が難しいマクロ経済状況が依然として続いていることを表している。家計の予算制約や企業の競争環境を踏まえると、輸入原材料価格の高騰が消費者物価全体の持続的な上昇に繋がる可能性は低い。
輸入物価の上昇による物価上昇は、家計の購買力が高まらないもとでは一時的なものに止まる。持続的な物価上昇には、賃上げによる家計の購買力の引上げが必要である。引き続き企業の価格設定行動や予想インフレ率に変化がみられるものの、需給ギャップや予想インフレ率の動向を踏まえると、2023 年度末に「物価安定の目標」を達成するのは難しい。
賃金と物価の持続的な上昇には、企業の生産性向上が欠かせず、人的資本投資等によるイノベーション力の強化や、スタートアップ育成等による新陳代謝の活発化と企業の構造改革を支援する地域金融機関の取り組みが重要である。
ということは、日銀が連続指値オペを実施したのは、物価の上昇リスクよりも経済の下押しリスクを最も気にしているということだろう。物価については、消費者物価の前年比は、2022 年度前半は資源価格の高騰等によって2%近傍で推移すると考えているものの、内需の回復が十分ではなく、企業にとって製品価格へのコスト転嫁が難しいマクロ経済状況が依然として続いているとの認識だ。輸入物価の上昇による物価上昇は、家計の購買力が高まらないもとでは一時的なものに止まると考えている。従って、長期金利の上昇が日本経済にとって最大のリスクであり、連続指値オペを実施したということなのだろう。
しかしながら、物価の上昇リスクについて、日銀は楽観的過ぎるのではないだろうか?
日銀も指摘しているように、人的資本投資等によるイノベーション力の強化や、スタートアップ育成等を通じて生産性が向上し、経済が成長するのであれば、仮に物価が上昇したとしても対応は可能だが、そのような経済成長が実現できない中での物価上昇は日本経済にとって悪影響しかないと私は思う。明らかに更なる物価上昇リスクが高まっている状況下、自国通貨安政策に繋がる可能性のある指値オペ(金融緩和政策)のリスクは日銀が思っている以上に大きいと思う。
年初来日米の金利差を受けて円安は進んでいるが、指値オペを見せられた市場参加者は、黒田日銀総裁は、円安が全体として経済と物価をともに押し上げることで、日本経済にポジティブに働くと考えていると思うのが自然だ。既に大幅に上がっている輸入物価は、円が売られれば更に上がるだろう。日本では、悪い物価上昇がこれから始まる可能性が高い。

株式会社ランプライターコンサルティングは、当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。当サイトでは、信頼できる情報源から得た情報を、確実に掲載するようあらゆる努力をしておりますが、株式会社ランプライターコンサルティングは、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。当サイトに掲載されている全ての情報は、その時点の情報が掲載されており、完全性、正確性、時間の経過、あるいは、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。また、あらゆる種類の保証、それが明示されているか示唆されているかにかかわらず、また業務遂行、商品性、あるいは特定の目的への適合性への保証、また、これらに限定されない保証も含め、いかなることも保証するものではありません。
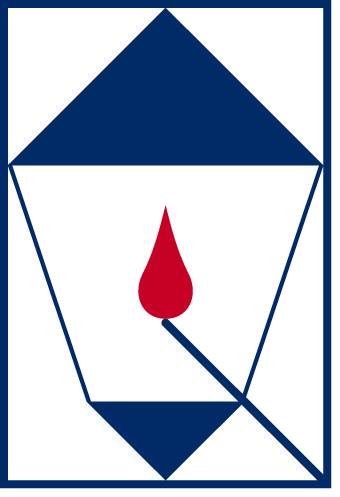



コメント