暇な特に 篠原金融塾 FRBがYCC ?
- 篠原竜一 代表取締役社長

- 2019年5月13日
- 読了時間: 3分
FRBのラエル・ブレイナード理事は先頃、日本銀行が実施している長期金利に明確な誘導目標を設ける金融政策について、FRBも検討すべきか問題提起した。1920-30年代には世界大恐慌を受け、米国でも長期金利を誘導するような政策が実施されたこともあり、特別騒ぐことではないことなのかもしれない。
しかしながら、世界中に大きな影響を与える基軸通貨国のアメリカの金融政策においてイールドカーブコントロール=YCCを導入することを検討しているなんて、正直これにはびっくりだ。
そもそもFRBはリーマンショック後に大量に米国債、米国モーゲージ債を購入、市場を支えた。これが金融引締めを実施しても長期金利が上がらない理由だった。売り手であるはずのFRBが売らないからだ。
そのFRBもやっとバランスシートの削減を始めたが、このオペレーションを9月にやめることを既に公表している。それに加えて、FRBが10年債の金利水準を維持することになれば、ますます金利は動かないし、上がらない。
20年以上も前から、市場との対話を重視してきたFRB。金融政策の透明性が高まり、効率的な金融政策を実施することにより、市場の変動率(=ボラティリィティ)は低下してきた。ボラティリティ(=リスク)が低下すればリターンも限られる。値幅が限られるようになってきたので、反対に動いたときに振り落とされる市場参加者が少なくなった。
ファンダメンタルズから考えるとグローバル化を受けて世の中はどんどん効率化された。物の値段は上がらない。インフレを心配しないといけない先進国はない。景気が良いという理由だけでは市場金利が大きく上昇することは考えにくいということになる。
そして投資家は少しでも金利が高い商品に投資するようになる。FRBが利回り誘導目標をコミットしてしまうとそれを試す投資家はいなくなる。こういう市場は歪んでいく。
株式会社ランプライターコンサルティングは、当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。当サイトでは、信頼できる情報源から得た情報を、確実に掲載するようあらゆる努力をしておりますが、株式会社ランプライターコンサルティングは、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。当サイトに掲載されている全ての情報は、その時点の情報が掲載されており、完全性、正確性、時間の経過、あるいは、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。また、あらゆる種類の保証、それが明示されているか示唆されているかにかかわらず、また業務遂行、商品性、あるいは特定の目的への適合性への保証、また、これらに限定されない保証も含め、いかなることも保証するものではありません。
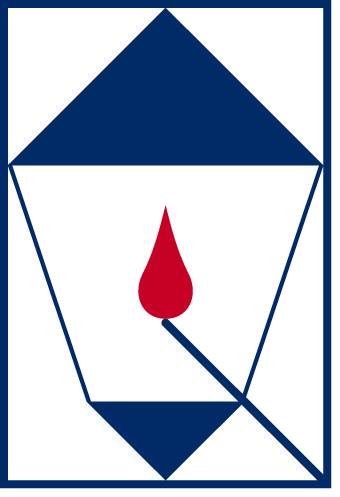



コメント